【京都ハック】敬老乗車証(敬老パス)は本当にお得なのか?
京都市にお住まいの高齢者の方に交付される「敬老乗車証」。
市バスや地下鉄などを格安、あるいは無料に近いかたちで利用できる制度ですが、近年その内容が大きく変わりつつあります。
敬老乗車証の歴史と変遷
京都市の「敬老乗車証」制度は、1973年(昭和48年)にスタートしました。
当初は70歳以上の高齢者に無料で市バス・地下鉄などが乗り放題になる制度で、長年親しまれてきました。
ところが、2005年に申請制と負担金制度が導入され、有料化の第一歩が始まります。
その後も制度は見直され続け、2022年には所得に応じた段階的な負担金、2023年には回数券方式の導入、そして交付年齢の75歳への引き上げも始まりました。
制度発足から50年以上が経ち、今や「完全無料」とはいえないこのパス。
本当にお得なのか、実際の運賃と比較してみる必要が出てきたのです。
👛 なぜ竹田駅で一旦分かれて、京都駅で合流するのか
うちでは、だいたい親とは竹田駅で一旦分かれます。
理由はカンタン。竹田で親が地下鉄に乗り換えると60円安くなるからです。
それに子が付き添うと260円高くなるからです。
以下の表をご覧いただくと、その意味がはっきりわかります。
| 利用者 | 区間 | 運賃 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 親(敬老パスあり) | 新田辺 → 竹田(近鉄) | 430円 | 敬老パスは近鉄に使えないため実費 |
| 竹田 → 京都(地下鉄) | 0円 | 地下鉄は敬老パスの対象で無料 | |
| 合計 | 430円 | ||
| 子(一般利用) | 新田辺 → 京都(近鉄直通) | 490円 | 乗換なし・最短最安 |
| 新田辺 → 竹田(近鉄)+竹田 → 京都(地下鉄) | 690円 | 親に合わせると260円高くなる。だから京都駅で親を迎えに行け。260円あれば、あんパンと牛乳が買えるぞ。 |
親は竹田で乗り換えないと60円高くなるだけとも言える。
でもその60円を気にしない人は、そもそも敬老パスを必要としないのかもしれない。
2025年現在の負担金制度(参考)
- 非課税世帯:9,000円
- 年収200万円未満:15,000円
- 年収200〜400万円未満:30,000円
- 年収400〜700万円未満:45,000円
※交付年齢も段階的に75歳以上に引き上げ中。
また、2023年からは回数券方式(プリペイド型)も選択可能になりました。
何回乗れば元が取れる?
敬老パスの自己負担額は、年間9,000円〜45,000円(2025年現在)と世帯収入に応じて変わります。
では、実際にどれくらい使えば元が取れるのかを計算してみましょう。
市バス・地下鉄の初乗り運賃は現在230円,220円。
それを基準に、単純な市バスの乗車回数で見てみると――
- 9,000円コースなら、たった 20回(片道)で元が取れる
- 45,000円コースでも、約 196回(=98往復)で元が取れる
通院・買い物・趣味のお出かけで月に4〜5往復する方なら、
多くのケースで自然と元は取れている計算になります。
敬老乗車証で無料になる主な施設(2025年現在)
敬老パスを提示することで、以下のような公共施設が無料または割引になります。
- 京都市動物園
- 京都市京セラ美術館(旧・京都市美術館)
- 京都市考古資料館
- 京都市青少年科学センター
- 京都市平安郷市民プール(夏季のみ)
- 市営体育館・トレーニングルームの利用料減免
※施設によって利用可能な年齢や曜日が異なる場合があります。事前に各公式サイト等でご確認をおすすめします。
まとめ|制度を理解して“賢く”使おう
敬老パスは、制度の変更によってお得度が変わるものになってます。
一昔前の「完全無料」で安いイメージで購入してしまうと、損をしてしまうことも…。
ご自身のライフスタイルに合わせて必要かどうか判断が必要ですね。
乗り換えを工夫したり、制度の仕組みをきちんと理解したり、
無料で使える施設も上手に活用すれば、敬老パスはもっと“お得な味方”になります。
京都らしい移動の知恵、楽しみながら取り入れていきましょう。
正直、年を重ねれば「無料で乗れる」と期待していた人も多かったはずです。
わたしも、その一人でした。
※本記事は2025年7月時点の制度をもとに作成しています。制度の詳細・最新情報は京都市公式サイトをご確認ください。
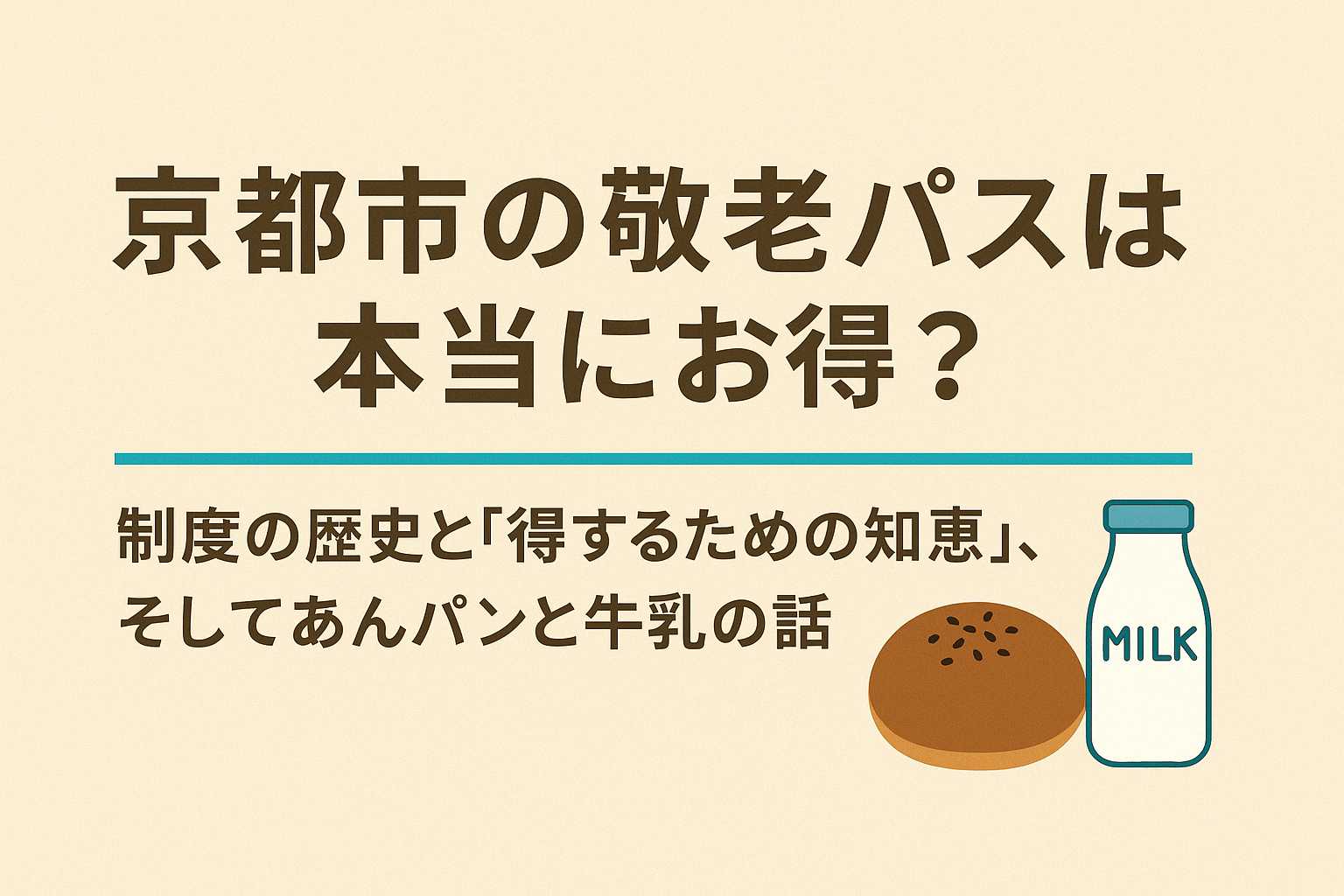

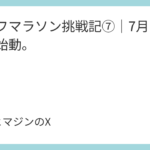
コメント